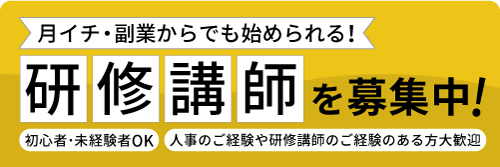1on1ミーティングの効果がないと諦めていませんか?:厚生労働省データが解き明かす、離職を防ぐ4つの成功戦略

「うちの1on1ミーティングは時間の無駄」「部下が本音を話してくれない」と、その効果を諦めていませんか? 離職の決定的な要因は、給与ではなく「人間関係」や「仕事への不満」にあることが、厚生労働省の複数の調査で明らかになっています。
本記事は、活発な労働市場の中で人材流出が止まらない根本原因を、最新の政府統計データに基づいて徹底分析します。そして、そのデータから導き出される、上司と部下の間に信頼関係を築き、離職の連鎖を断ち切るための1on1ミーティングの効果的な実践ノウハウと、4つの成功戦略を具体的にお伝えします。
1. 労働市場の現状:活発化する「大転職時代」の真実
1-1. 雇用の流動化と深刻な人手不足
日本の労働市場は、かつてないほどに流動性が高まっています。厚生労働省が実施した「令和5年雇用動向調査」によると、入職率は16.4%、離職率は15.4%と、いずれも前年を上回る結果となりました。これは、多くの人々が新たな職を求めて積極的に移動している現状を明確に示しています。
この流動化は、企業経営に直接的な影響を及ぼしています。「令和6年版 労働経済白書」では、求人が底堅く推移している一方で、企業の倒産件数は増加しており、特に「人手不足関連倒産」が調査開始以降過去最高を記録したと報告されています 。この事実は、労働力の需給ギャップが深刻な経営課題となっていることを物語っています。
1-2. 転職者の賃金動向:求職者が求める「より良い条件」とは
労働市場の活発化は、従業員にとって有利な状況を生み出しています。転職者の賃金変動に関する調査では、前職と比べて賃金が増加した割合が40.0%に達し、前年より1.4ポイント上昇しました 。一方で、減少した割合は28.9%で、前年より4.3ポイント低下しています 。このデータは、単に不満から離職するのではなく、より良い条件を求めて能動的に行動し、実際にそれを実現している人々が多いことを示しています。企業が人材を確保するためには、単に現状維持に努めるだけでなく、従業員の期待に応えるための抜本的な対策が不可欠となっています。この動向は、企業が自社の魅力を高め、従業員の定着を図るための非金銭的要因にも焦点を当てる必要性があることを強く示唆しています。
2. 離職理由の深層:厚生労働省データが明らかにする「本当の不満」
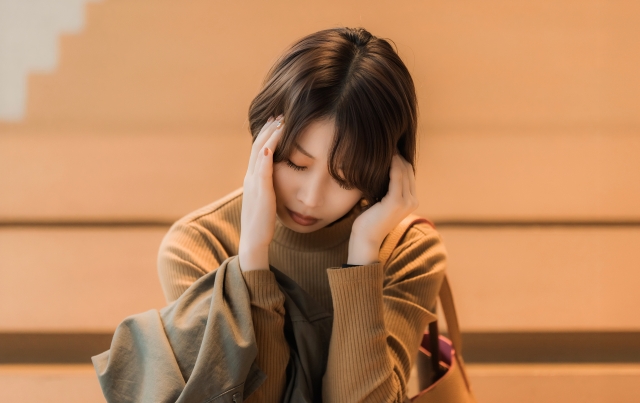
2-1. 離職理由の全体像:金銭的要因だけではない
「令和5年雇用動向調査」の離職理由を詳細に分析すると、賃金や労働条件といった金銭的・待遇的要因だけでなく、より個人的で内面的な要因が離職の大きな動機となっていることがわかります。離職理由全体のうち、結婚、出産・育児、介護・看護、その他の個人的な理由を合わせた離職率は、令和5年に11.4%となり、前年から0.4ポイント増加しました。この事実は、企業が従業員のライフステージやキャリアの希望により深く寄り添うことが、人材定着において重要であることを示唆しています。
2-2. 年齢・性別で異なる離職理由の傾向分析
離職の理由は、年齢や性別によって顕著な違いが見られます。「令和5年雇用動向調査」のデータは、その多様な実態を浮き彫りにしています。
厚生労働省雇用動向調査 離職理由トップ5(年齢・性別別)
| 年齢層 | 男性の主な離職理由 | 女性の主な離職理由 |
| 19歳以下 | 労働時間、休日等の労働条件が悪かった (28.4%) | 職場の人間関係が好ましくなかった (22.9%) |
| 20~24歳 | 労働時間、休日等の労働条件が悪かった (11.4%) | 労働時間、休日等の労働条件が悪かった (15.6%) |
| 25~29歳 | 仕事の内容に興味が持てなかった (14.1%) | 労働時間、休日等の労働条件が悪かった (18.4%) |
| 35~39歳 | 職場の人間関係が好ましくなかった 給料等収入が少なかった (11.3%) | 職場の人間関係が好ましくなかった (13.1%) |
| 45~49歳 | 職場の人間関係が好ましくなかった (14.6%) | 職場の人間関係が好ましくなかった (18.7%) |
| 50~54歳 | 仕事の内容に興味が持てなかった (10.9%) | 定年・契約期間の満了 (10.1%) |
この表が示すように、男性の20代後半や50代前半では「仕事の内容に興味が持てなかった」という理由が上位に挙がり、仕事へのやりがいや成長機会を求める傾向が強いことがわかります。特に、男性の離職理由として前年と比べて上昇幅が最も大きいのは「仕事の内容に興味を持てなかった」(2.9ポイント)です。一方、多くの年齢層、特に女性の10代や30代後半、40代後半、50代後半においては、「職場の人間関係が好ましくなかった」が主要な離職理由となっています 。このデータは、職場の人間関係や業務内容への不満が、従業員のエンゲージメントを低下させ、最終的に離職を促す決定的な要因となることを示唆しています。労働市場の活発化は、これらの不満を抱える従業員にとって、より良い環境を求めて転職する機会を提供しているのです。
3. ワークエンゲージメントの低下:政府も注目する組織の活気
3-1. エンゲージメント調査の重要性:組織の健康状態を可視化
離職の根本的な原因が人間関係や仕事内容にあることを踏まえ、企業は従業員のエンゲージメント(組織への愛着や仕事への熱意)を高める努力が求められます。この点において、政府機関自身も率先してエンゲージメントの可視化に取り組んでいます。厚生労働省は、職員のエンゲージメント低下を早期に発見し、ケアするための取り組みとして、原則入省8年目までの職員を対象に毎月エンゲージメントサーベイを実施しています。これは、エンゲージメントが組織の健全性を測る重要な指標であるという認識が、公的機関にも浸透していることを示すものです。
また、厚生労働省の「令和元年版労働経済白書」では、将来のキャリア展望を明確化することが「働きがい」の向上につながると指摘されています。この「働きがい」は、仕事への熱意、活力、没頭といったワークエンゲージメントの構成要素であり、生産性や定着率に大きな影響を与えます。離職理由のデータが示唆するように、多くの従業員が将来の展望を見出せず、仕事への興味や関心を失うことが離職の一因となっている可能性を示唆しています。この問題に積極的に取り組むことが、人材の定着に直結する重要な課題なのです。
出典元:人事院「公務のためのキャリア形成支援ガイドブックVer.1.0」
3-2. ハラスメント対策とコミュニケーションの関連性
もう一つの重要なデータは、職場環境の改善が従業員のエンゲージメントに与える影響です。「令和5年度 職場のハラスメント実態調査報告書」によると、ハラスメント防止対策に取り組んだ企業が最も多く挙げた副次的効果は、「職場のコミュニケーションが活性化する/風通しが良くなる」ことで、回答企業の39.1%に上りました。これは、ハラスメントという負の事象への対策が、結果としてコミュニケーションという正の側面に好影響を与えることを示しています。
ハラスメント対策の副次的効果
| 効果 | 回答企業の割合 |
| 職場のコミュニケーションが活性化する/風通しが良くなる | 39.1% |
| 会社への信頼感が高まる | 34.7% |
このデータから、意図的な取り組みを通じて職場内のコミュニケーションを改善することが、従業員の信頼感を高め、組織全体の健全性を向上させる上で非常に効果的であることが明らかになります。
出典元:厚生労働省「令和5年度 職場のハラスメント実態調査報告書」
4. 解決策としての1on1ミーティング:データが導き出す本質的な効果
厚生労働省のデータが明らかにした「本当の不満」——すなわち、人間関係の不満、仕事内容への興味の喪失、将来のキャリア展望の不明瞭さといった非金銭的要因は、個別かつ継続的な対話によってしか解決できません。ここで最も有効なツールとなるのが、戦略的に設計された1on1ミーティングです。
4-1. 離職の根本原因に効く!1on1ミーティングがもたらす4つの具体的効果
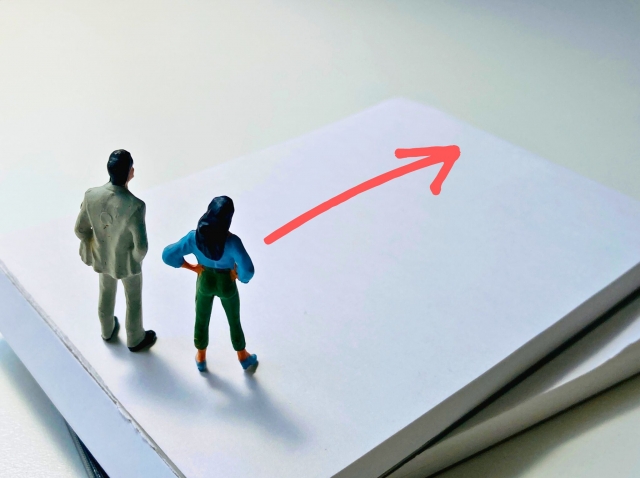
1on1ミーティングは、前述のデータが示す離職の根本原因に、直接的かつ人道的にアプローチする手段であり、その効果は多岐にわたります。
- 効果①:職場の人間関係を改善し、心理的安全性を高める
離職理由のトップクラスに挙がる「職場の人間関係」の問題は、信頼関係の欠如から生じます。定期的な1on1ミーティングは、部下が安心して本音を話せる心理的安全性の高い機会を提供します。これにより、潜在的な不満を早期に察知し、解決に向けた対話を促すことができます。
- 効果②:仕事への興味・関心を再燃させ、モチベーションを向上
「仕事の内容に興味が持てなかった」という不満は、特に若年層やミドル層の男性の離職理由として顕著です。上司と部下が業務の目的や意義、達成感について深く対話することで、部下は自身の仕事が組織にどのように貢献しているかを再認識できます。これにより、業務への関心を再燃させ、仕事への意欲を高めることが可能です。
- 効果③:キャリアパスを明確にし、「働きがい」を醸成
上司からの適切なフィードバックを通じて将来のキャリア展望を明確化することは、「働きがい」を高める取り組みとして極めて重要です。1on1ミーティングは、部下のキャリアプランやスキル開発について具体的に話し合う絶好の機会です。部下が自身の将来への展望を持つことができ、長期的な貢献意欲が高まります 。
- 効果④:ハラスメント防止とエンゲージメント向上の両立
オープンで建設的な対話が常態化することで、ハラスメント行為が発生しにくい、心理的安全性の高い職場環境が醸成されます。これにより、ハラスメント対策がもたらす副次的効果である「コミュニケーションの活性化」や「会社への信頼感の向上」を、意図的に創出することができます。結果として、ワークエンゲージメント全体が向上し、組織のパフォーマンス最大化につながります。
出典元: 厚生労働省「令和元年版労働経済白書」
5. 今すぐ実践できる1on1ミーティングの設計と運用
厚生労働省のデータから導き出された離職の本質的な原因を解決するためには、単に1on1ミーティングを実施するだけでなく、その目的と内容を明確に設計することが不可欠です。
5-1. 離職を防ぐ「傾聴」と「質問」の具体的なコツ
1on1ミーティングの成否は、上司側のスキルに依存します。上司が一方的に話したり、業務の進捗確認や「詰め」になったりすると、部下は本音を話さず、ミーティングは形骸化し、逆にストレスの原因となります。
傾聴のコツ:心理的安全性を高める
- 部下の話に耳を傾ける(主役は部下): 1on1は部下のための時間です。上司は話したいことを我慢し、部下の話に集中して耳を傾けることが鉄則です。
- ノンバーバルコミュニケーション: 頷きや相槌を有効活用し、特にオンライン会議では対面以上に大きな反応を意識することで、部下が話しやすい雰囲気を作ります。
- 共感と復唱: 部下の言葉を言い換えたり、「〇〇とは、つまり△△ということですか?」と確認したりすることで、話を聞いていること、理解しようとしている姿勢を伝えることが重要です。
質問のコツ:本音と成長を促す
- 問いかけで思考を深める: 上司が正解を与えるのではなく、「なぜそうなったと思うか?」「次にどうしたらいいか?」といった質問で、部下自身に解決策を考えさせるプロセスをサポートします。この主体的な思考の機会が、部下の自律的な成長を促します。
- 本音を引き出す質問: 関係性に応じて「正直どうですか?」といった問いかけを会話に取り入れることで、部下の建前ではない真意を引き出しやすくなります 。
5-2. 目的別1on1ミーティング:離職原因に直結する3つの焦点
闇雲に雑談をするのではなく、従業員の不満に直接アプローチするため、以下の3つの観点に焦点を定めた1on1ミーティングを定期的に実施することが推奨されます。
- コンディション(人間関係・心身の健康)
- 焦点: 「職場の人間関係が好ましくなかった」という離職理由の解決。
- 具体的な対話: 部下の心身の健康状態や、業務におけるストレス、チーム内のコミュニケーションの状況について耳を傾けます。プライバシーに配慮しつつ、「最近の体調はいかがですか?」、「チームとの協力体制で改善できる点はありますか?」といった質問で、潜在的な不満を早期に発見します。
- パフォーマンス(仕事の興味・やりがい)
- 焦点: 「仕事の内容に興味が持てなかった」という不満の解消。
- 具体的な対話: 日々の業務の進捗や目標の達成度について確認し、特に部下が「やりがいを感じた瞬間」や「達成感」に焦点を当てます 。これにより、部下は自身の業務の意義を再認識し、「仕事への意欲」を再燃させることが可能です 。
- キャリア(将来の展望・成長意欲)
- 焦点: 「働きがい」を高める「将来のキャリア展望」の明確化。
- 具体的な対話: 部下が描く長期的なキャリアプランや、そのために今後習得したいスキル、経験について話し合います。部下が自身の将来への展望を持つことができ、会社への長期的な貢献意欲が高まります。
5-3. 継続的な運用とフィードバック:データを活かすPDCAサイクル
1on1ミーティングの効果は、短期間で劇的に現れるものではありません。単発で終わらせるのではなく、継続的な運用と改善が不可欠です。
- 振り返りとデータの蓄積: 1on1で話した内容は、必ずメモを取り、記録として蓄積することが重要です。これにより、部下の成長の軌跡を時系列で確認でき、次回のフィードバックやキャリア支援の精度を高めることができます。
- エンゲージメントとの連携: 厚生労働省が自組織で行っているように、エンゲージメントサーベイなどのツールを併用し、1on1ミーティングの実施が従業員のエンゲージメントや離職率にどのような影響を与えているかを客観的に測定することが重要です。
- 継続的な改善(PDCA): データを活用したPDCAサイクルを回すことで、1on1ミーティングは単なる対話の場から、組織の課題を解決する戦略的な人事施策へと進化します。定期的な振り返りと改善を通じて、離職の根本原因に継続的にアプローチすることが、その効果を最大化する鍵です。
6.まとめ
厚生労働省の調査によると、離職の主な原因は給与だけでなく、「職場の人間関係」や「仕事への不満」にあります。このような「大転職時代」において、従業員の定着には、彼らの心理的・専門的な欲求に応えることが不可欠です。
1on1ミーティングは、これらの課題を解決するための最も有効な手段です。定期的な1on1を通じて従業員一人ひとりの声に耳を傾けることで、彼らが抱える不満を早期に発見し、キャリア成長を支援できます。これにより、従業員が「辞めたい」と感じる前に「この会社で働き続けたい」と思えるような、強固な職場文化を築くことができます。
1on1を成果に変えるツール:Teichaku Marker
1on1の効果を最大化するには、「マネージャーの運用負担」と「効果測定の難しさ」を克服する必要があります。
定着支援ツール「Teichaku Marker」は、1on1の効果をデータで証明し、離職リスクを解消します。離職の根本原因を定期的なサーベイで特定し、リスクの高い社員には最適な1on1のテーマを自動で提案します。
データに基づいた離職防止戦略にご興味があれば、ぜひご相談ください。
▶▶▶ Teichaku Markerの無料相談はこちらから ◀◀◀