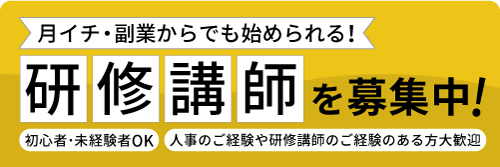従業員エンゲージメント向上施策の羅針盤:定義から具体的な打ち手、成功事例まで徹底解説

現代の企業経営において、単なる福利厚生の充実や賃上げだけでは、従業員の定着や生産性向上に直結しないケースが増加しています。これからの時代に求められるのは、従業員一人ひとりが仕事にやりがいを感じ、組織に貢献したいと自発的に思える状態、すなわち【エンゲージメント向上】です。本記事は、従業員エンゲージメントの本質から、自社に合った具体的な施策、その効果測定方法までを網羅的に解説する「羅針盤」となることを目指します。
1.従業員エンゲージメントの本質を理解する
エンゲージメントには二つの概念が存在します。一つは、仕事に焦点を当てた「ワークエンゲージメント」で、仕事への「活力」「熱意」「没頭」があるポジティブな心理状態を指します 。これは、従業員個人と仕事の関係性に着目した概念です。
もう一つは、「従業員エンゲージメント」で、組織への貢献意欲を指します 。従業員が組織の目指す方向性を理解し、それが自身の目標と重なることで、自発的に貢献したいと考える状態です 。
企業の持続的な成長には、この二つのエンゲージメントをバランス良く高めることが不可欠です。仕事にやりがいを感じつつも、組織への貢献意欲が低い場合、より良い待遇を提示する他社に転職してしまうリスクがあります。逆に、組織への貢献意欲が高くても、仕事にやりがいを感じられなければ、生産性の低下につながります。従業員が仕事そのものに深いやりがいを持ち、その延長線上で組織への貢献意欲を高めるという両輪での取り組みが、エンゲージメント施策の成功を左右する鍵となります。
2.現状を把握し、課題の根本原因を特定する
エンゲージメント施策を立案する第一歩は、自社の現状と課題を客観的に把握することです。厚生労働省が公表した「令和5年雇用動向調査」によると、2023年の入職率は16.4%、離職率は15.4%となり、いずれも前年を上回っています。このデータは、労働市場が活発化し、多くの企業が人材の流動性に直面している現状を浮き彫りにしています。
この離職の背景にある具体的な理由を年代別に分析すると、世代ごとに異なるエンゲージメントの課題が見えてきます。同調査によると、転職入職者が前職を辞めた主な理由は以下の通りです。
| 性別 | 年齢 | 離職理由のトップ | 割合(%) |
|---|---|---|---|
| 男性 | 19歳以下 | 労働時間、休日等の労働条件が悪かった | 28.4 |
| 20〜24歳 | 労働時間、休日等の労働条件が悪かった | 11.4 | |
| 25〜29歳 | 仕事の内容に興味が持てなかった | 14.1 | |
| 30〜34歳 | 給料等収入が少なかった | 14.1 | |
| 35〜39歳 | 職場の人間関係が好ましくなかった/給料等収入が少なかった | 11.3 | |
| 40〜44歳 | 職場の人間関係が好ましくなかった | 14.6 | |
| 女性 | 19歳以下 | 職場の人間関係が好ましくなかった | 22.9 |
| 20〜24歳 | 労働時間、休日等の労働条件が悪かった | 15.6 | |
| 25〜29歳 | 労働時間、休日等の労働条件が悪かった | 18.4 | |
| 30〜34歳 | 職場の人間関係が好ましくなかった | 9.6 | |
| 35〜39歳 | 職場の人間関係が好ましくなかった | 13.1 | |
| 40〜44歳 | 労働時間、休日等の労働条件が悪かった | 17.6 |
このデータから、若年層(特に男性)は「労働時間」や「仕事内容」といった労働環境に直接的な課題を感じている傾向が分かります 。一方、中堅・ベテラン層は「給料」や「人間関係」といった、より組織や評価制度に関わる課題を離職の主要因として挙げています 。この年代別の傾向は、エンゲージメント施策が画一的であってはならないことを強く示唆しています。
3.課題別に見る、多角的なエンゲージメント向上施策

先ほど特定した課題に対し、厚生労働省が具体的に推奨・支援する多角的な施策は、相互に連携し、従業員のエンゲージメントを多方面から支えるエコシステムを形成しています。
3-1. 労働時間・柔軟な働き方の改善
若年層の離職理由に対応するため、長時間労働の是正、休息の確保、年次有給休暇の取得促進、フレックスタイムやテレワークなど多様な勤務形態の導入が推進されています 。
3-2. 公正な評価と待遇の確保
中堅層の不満解消には、非正規雇用労働者と正規雇用労働者の不合理な待遇差をなくす「同一労働同一賃金」の原則が適用されています 。また、非正規雇用労働者の正社員化や処遇改善に取り組む事業主を支援する「キャリアアップ助成金」も活用できます 。
3-3. 心身の健康と安全の確保
エンゲージメントの土台となる心身の健康を支えるため、厚生労働省は「セルフケア」「ラインケア」「事業場内産業保健スタッフによるケア」「事業場外資源によるケア」の4種類のメンタルヘルスケアの連携を推奨しています 。また、「ストレスチェック」を活用した職場環境改善も有効です 。
3-4. 個人の成長とキャリア形成の支援
若年層の課題に対応するため、職業能力開発を金銭的に支援する「人材開発支援助成金」や「教育訓練給付制度」が用意されています 。また、「キャリアコンサルティング」や「リスキリングを通じたキャリアアップ支援事業」も、従業員の自律的なキャリア形成を支援します 。
これらの施策は、個別に存在するのではなく、相互に作用することで、従業員のエンゲージメントを体系的に高める効果が期待できます。
4.先進企業が導入する具体的なツールと実践例
理論的な施策を現実のものとするには、具体的な実践例を参考にすることが有効です。厚生労働省の「グッドキャリア企業アワード」や「快適職場づくり事例集」は、そのヒントに満ちています。
4-1. キャリア形成支援の実践例
厚生労働省がキャリア形成支援の好事例として紹介する明治安田生命保険相互会社は、従業員の職務経歴やスキル、評価情報を一元管理するシステムを構築しました。これにより、従業員自身がキャリアのロールモデルを検索したり、必要な知識やスキルを把握したりできる環境を提供し、主体的なキャリア形成を促しています 。また、伊藤忠テクノソリューションズ株式会社や株式会社アシックスは、全従業員に対し、キャリアコンサルタントとの定期面談や、キャリアプランを記入するCDP(Career Development Plan)シートの作成を義務化しています 。
4-2. 物理的な職場環境改善の実践例
物理的な環境改善は、従業員の心身の健康と生産性に直結します。厚生労働省の「快適職場づくり事例集」は、その具体的なヒントを提供しています 。
- 視環境の改善:天窓を設けて自然光を取り入れたり、天井の高い倉庫に補助照明を設置して作業者の眼精疲労を軽減したりする事例が紹介されています 19。
- 音環境の改善:低騒音型コンプレッサーの導入や、プリンターの「防音カバー」の設置など、騒音を軽減し、集中できる環境を整備する取り組みが効果を上げています 。
- 疲労回復支援施設の整備:冷暖房完備の休憩室や仮眠室、広い浴槽のお風呂の設置など、従業員の心身の健康とリフレッシュを支援する多様な施設整備は、「会社は従業員を大切にしている」というメッセージを伝え、組織への信頼を深める効果があります 。
出典元:厚生労働省/中央労働災害防止協会「快適職場づくり事例集」
5.成功事例から学ぶ、エンゲージメント向上のヒント
先ほどの事例をさらに深く分析することで、エンゲージメントを飛躍的に向上させるための普遍的なヒントを抽出できます。
ヒント1:経営層の強いコミットメントとビジョンの共有
厚生労働省の資料でも、エンゲージメント向上には「トップからのメッセージの発信」が大切だと指摘されています 。成功事例を見ると、経営トップが中期経営計画の策定メンバーに中堅社員を選抜したり、食事会を通じて全従業員と個別面談を実施したりしています。これにより、組織の目指す方向性(ビジョン)が従業員に深く浸透し、自身の仕事が会社に貢献しているという実感が、組織への貢献意欲を高めます。
出典元:厚生労働省「働きがいのある職場づくりのための支援ハンドブック」
ヒント2:仕事の属人化解消とチームワークの強化
働き方改革においては、男性の育児休業取得を促進し、育児・家事への参加を促すことが重要な課題とされています 。育児休業取得の際には、業務の引き継ぎがスムーズに行われるよう計画的に進めることが、特定の個人にしかできない「仕事の属人化」を解消し、チーム全体で業務を進める意識を向上させることにつながります。この結果、業務の円滑化だけでなく、従業員間の相互理解が深まり、コミュニケーションが活性化されることで、離職理由の上位に挙げられる「職場の人間関係」の改善にも寄与する相乗効果が期待できます 。
出典元:厚生労働省「PDCAサイクルを実践して生産性を高めよう」
厚生労働省「働きがいのある職場づくりのための支援ハンドブック」
ヒント3:ライフイベントに寄り添う柔軟な制度設計
株式会社資生堂の事例では、育児・介護休業や短時間勤務制度を充実させた結果、育児休業後の復職率が94.9%という高水準を達成しています。このようなワーク・ライフ・バランスへの配慮は、従業員が「この会社なら人生のあらゆるステージで安心して働き続けられる」という長期的な信頼感と愛着を育むことにつながります。
6.施策の効果測定と継続的な改善サイクル
せっかくの施策も、「やりっぱなし」にしては意味がありません。その効果を測定し、継続的に改善していくための文化を根付かせることが不可欠です。
6-1. 効果測定のための指標
厚生労働省は、働き方改革の効果測定に活用できる「働き方・休み方改善指標」を推奨しています 。以下のような指標を測定することで、施策の効果を客観的に把握できます 。
- 年次有給休暇取得率
- 労働生産性
- 長時間労働者の割合
6-2. 継続的な改善のフレームワーク:PDCAサイクル

厚生労働省は、業務改善の王道としてPDCAサイクル(Plan-Do-Check-Action)の活用を推奨しています。
- Plan(計画):漠然とした目標ではなく、具体的な「定量目標」を設定し、期間を定めます。
- Do(実行):計画に沿って施策を実行し、次の評価段階で活用できるよう、活動記録を詳細に残します。
- Check(評価):なぜその結果になったのか、要因分析を深く検討します。
- Action(改善):評価結果に基づき、問題点を克服するための改善案を考えます。うまくいった点は継続し、うまくいかなかった点は次の計画に反映させます。
このPDCAサイクルを回す過程自体が、従業員のエンゲージメントを高める重要な機会となります。施策の効果を測定し、継続的に改善する文化こそが、従業員が会社に深く関与する機会を生み出し、真の【エンゲージメント向上】を長期的に実現する基盤となるのです。
出典元:厚生労働省「PDCAサイクルを実践して生産性を高めよう」
7.まとめ
本記事では、厚生労働省の信頼性の高いデータに基づき、従業員エンゲージメントの羅針盤として、その定義から実践、そして継続的な改善プロセスまでを包括的に解説しました。ワークと組織、両方へのエンゲージメントを高めることの重要性、年代ごとの離職理由が示す課題、働き方改革関連法やキャリア形成支援、そして先進企業の成功事例から得られるヒントを体系的に理解することで、自社に最適な施策が見えてきます。そして、PDCAサイクルを回し、効果を継続的に検証・改善する文化を根付かせることが、企業の持続的な成長に不可欠です。この「羅針盤」を手に、従業員一人ひとりが輝く職場づくりを今から始めてみましょう。
エンゲージメント施策は、組織や従業員一人ひとりの状況に合わせて、多角的なアプローチが必要です。しかし、多くの企業が「何から手をつければいいのか」「施策の効果が測定しにくい」といった課題に直面しています。
従業員エンゲージメントの羅針盤となる「Teichaku Marker」
この記事で解説した通り、従業員エンゲージメントを向上させるには、まず自社の課題を正しく把握することが不可欠です。しかし、厚生労働省のデータや一般的なアンケートだけでは、自社特有の「課題の根本原因」を見つけ出すのは難しいでしょう。
そこで、株式会社MASTが提供する「Teichaku Marker」が、貴社のエンゲージメント施策の羅針盤となります。Teichaku Markerは、独自のテクノロジーを駆使して、従業員の潜在的な離職リスクやエンゲージメントの現状を多角的に分析します。
Teichaku Markerが選ばれる3つの理由
- 潜在的な離職リスクを可視化 ー一般的なエンゲージメントサーベイでは見過ごされがちな、「離職の予兆」を独自のアルゴリズムで検知します。これにより、従業員が実際に退職を検討し始める前に、個別のフォローアップや対策を打つことが可能になります。
- 従業員の“本音”を引き出す独自調査ー 匿名性を担保しつつ、従業員が「なぜそう思うのか」という理由や背景まで深掘りする設問設計で、定量データだけではわからない従業員の“本音”を引き出します。これにより、表層的な不満だけでなく、真の課題を特定できます。
- 具体的な改善策までご提案ー分析結果は、単なるレポートに留まりません。蓄積されたデータと専門家の知見に基づき、「次に何をすべきか」という具体的なアクションプランをご提案します。これにより、分析結果を施策に直結させることができ、PDCAサイクルをスムーズに回すことが可能になります。
貴社のエンゲージメント向上を徹底サポート
Teichaku Markerは、「エンゲージメント施策の効果がわからない」「何から着手すべきか悩んでいる」といった課題を抱える企業に最適なソリューションです。
無料でご相談を承っております。貴社の現状や課題をヒアリングさせていただき、最適な解決策をご提案いたします。
貴社の従業員エンゲージメントを確実に向上させるために、ぜひ一度お気軽にご相談ください。▶▶▶ Teichaku Markerの無料相談はこちらから ◀◀◀