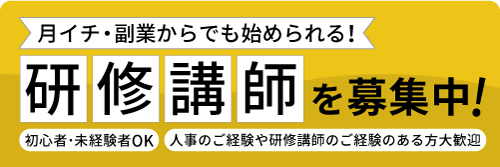【2025年最新版】離職予防の施策10選!定着率改善に導く実践的ステップと成功事例

現代の企業経営において、従業員の離職予防は最も重要な経営課題の一つです。労働力人口の減少が進む日本では、採用活動が年々難しくなっており、せっかく採用した人材をいかに定着させるかが企業の競争力を大きく左右します。
従業員が早期に離職すると、それまでに投じた採用や教育コストが無駄になるだけでなく、組織全体に深刻なダメージを与えます。この課題に正面から向き合い、戦略的に離職予防に取り組むことが、持続的な企業成長には不可欠です。
1. なぜ離職予防が重要か?知っておくべき3つのコストと最新データ
従業員の離職は、企業に甚大な影響をもたらします。ここでは、離職によって発生する3つのコストと、最新の離職率データからその深刻性を解説します。
離職がもたらす3つのコスト
- 金銭的コスト
- 採用広告費、人材紹介料、面接や選考にかかる時間的コストなど、従業員が1人離職するたびに、企業は新たな支出を余儀なくされます。さらに、新人教育やOJTに投じた投資も回収できません。
- 組織的コスト
- 人員が不足すると、業務が滞り、残された社員が業務をカバーせざるを得なくなります。その結果、長時間労働や負担感が増大し、さらなる離職を引き起こす「負の連鎖」が発生します。
- 特に、従業員数100人未満の中小企業では、大卒者の3年以内離職率が約50%に達しており、わずか一人の退職が組織全体の士気を下げ、大きなダメージを与えるのです。
- 社会的コスト
- 高い離職率は、企業のイメージを毀損し、外部からも「長く働けない会社」という認識が広まります。求職者は離職率を重視する傾向にあり、優秀な人材の獲得が困難になります。ブランドの毀損は、長期的に企業の存続を危うくする要因になります。
これらの事実から、離職予防は単なる人件費削減策ではなく、企業の存続と成長を左右する経営の最重要戦略であることがわかります。
2. 離職予防のための重要な10の施策
ここでは、効果的な離職予防に不可欠な10の施策を具体的に解説します。これらの施策は、従業員のエンゲージメントと定着率を向上させるために体系的に連携させることが重要です。
- 入社前後のオンボーディング強化
- 離職が最も多いのは入社から1年以内であり、その多くは「仕事の内容や環境が想定と違った」というミスマッチに起因します。これを防ぐためには、採用段階から企業が求職者に対し、仕事内容や組織の実態を良い面も悪い面も含めた、ありのまま提供する「RJP(Realistic Job Preview)」を導入し、採用時点での企業と求職者とのミスマッチを軽減することが大切です。
- さらに、入社直後にはメンター制度やウェルカムプログラムで、先輩社員が新入社員をサポートする体制を整え、安心して働ける環境を提供します。
- 定期的なキャリア面談・1on1
- 従業員が「自分の成長の道筋が見えない」と感じると、モチベーション低下から離職につながります。そこで有効なのが、定期的なキャリア面談や1on1です。上司が部下のキャリア志向や現状の課題を丁寧にヒアリングし、次のステップを一緒に考えることで「この会社で成長できる」という実感を持たせられます。
- サイバーエージェントの「月イチ面談」のように、単なる業務報告だけでなく、キャリアや価値観を共有する場として活用することが、エンゲージメント向上に繋がります。
- 公平で透明な評価制度
- 評価制度に不透明さがあると「努力しても報われない」という不満が生じ、離職理由になります。これを防ぐには以下のポイントが重要です。
- 評価基準の明確化: 成果だけでなく、チーム貢献やプロセスも含めた多面的な基準を設定する。
- 透明性の担保: 360度評価や複数の評価者を導入し、上司の主観に偏らない仕組みを整える。
- キャリアとの連動:評価によってどのようなスキルに達したら、昇進・昇給するかだけでなく、現在のスキルレベルと目指すべきスキルとの差を明確にすることで、次に必要なスキルと対応する研修機会を設定する。
- 評価制度に不透明さがあると「努力しても報われない」という不満が生じ、離職理由になります。これを防ぐには以下のポイントが重要です。
- ワークライフバランスの推進
- 過重労働や休暇の取りづらさは離職の大きな要因です。テレワーク、フレックスタイム、副業制度を導入し、多様な働き方を可能にします。ただし、制度を設けるだけでなく、実際に「休暇を気兼ねなく取れる雰囲気」や「業務効率化による残業削減」を伴わなければ効果は出ません。
- リクルートが推進する、年間休日145日や半期に一度の長期休暇「フレキシブル休暇」のように、制度を形骸化させない運用が重要です。
- 社内コミュニケーションの活性化と心理的安全性
- 人間関係の不和は離職理由の上位を占めます。これを解消するためには、社員が「何を言っても大丈夫」と感じられる心理的安全性の高い組織づくりが不可欠です。部署横断型のイベントや社内SNSを積極的に活用し、日常的な「雑談」を促すことで、孤立感を解消し、チームの一体感を高めます。
- 健康経営の推進
- 従業員が健康でなければ生産性は維持できません。定期健診やストレスチェックに加え、産業医やカウンセラーによる相談窓口を設けることが重要です。さらに、フィットネス費用の補助や健康的な社食の提供など、生活習慣の改善を支援する施策も効果的です。
- 管理職のマネジメント研修
- 上司との関係は離職理由の多くを占めます。上司の指導が厳しすぎる、あるいは関心が薄いと、部下は安心して働けません。そこで、管理職には傾聴力やコーチングスキルに加え、心理的安全性を高めるリーダーシップを学ぶ研修を徹底します。管理職の質を高めることが、組織全体の定着率を左右するのです。
- 従業員エンゲージメント向上
- 社員が「自分は会社に貢献したい」「必要とされている」と感じられる環境を整えることは、離職予防に直結します。社内提案制度やアイデアコンテストで社員の意見を尊重し、挑戦を評価する文化を醸成することで、エンゲージメントは自然と高まります。
- サイバーエージェントの「ジギョつく(新規事業提案制度)」などは、社員の挑戦心を刺激し、エンゲージメントを高める好例です。
- キャリアパスと研修制度の整備
- 将来のキャリアを描けない不安は、社員がより成長できる環境を求めて離職する大きな要因です。これを防ぐには、昇進・昇格の基準を明確にし、必要なスキルを習得できる研修制度を整えることが大切です。
- サイバーエージェントの「キャリチャレ(社内異動公募制度)」のように、社員の主体的なキャリア形成を支援する仕組みは、長期的な定着に繋がります。
- データ活用と定期サーベイ
- 離職予防施策は「やりっぱなし」にしてはいけません。従業員満足度調査やエンゲージメントサーベイを定期的に実施し、データを分析して課題を特定します。特に、退職者アンケートを収集・分析し「なぜ辞めたのか」という離職の根本原因を体系的に把握することで、同じ理由による離職の再発を防げます。
3. 離職予防の成功事例
ここでは、実際に高い定着率改善を実現した企業の具体的な事例を紹介します。
- サイバーエージェント
- 「月イチ面談」や「ジギョつく」「キャリチャレ」といった独自の制度を整備し、若手社員のキャリア自律を支援することで、離職率を大幅に低下させました。これらの制度は、社員が会社に貢献している実感や、成長できる環境を具体的に提供しています。
- リクルート
- 採用段階でのRJP(現実的な仕事情報開示)や、入社後のオンボーディングを徹底し、ミスマッチによる早期離職を防止しています。また、リモートワークやフレックスタイムなど柔軟な働き方を推進することで、社員のワークライフバランスを向上させ、高い定着率を維持しています。
- カネテツデリカフーズ
- 創業100年を超える老舗企業であるカネテツデリカフーズは、新入社員の離職率が50%を超える時期がありました。そこで、先輩社員が新人の相談役となる「マンツーマン制度」を導入し、きめ細かなサポートを行った結果、離職率を数%まで減少させることに成功しました。これは、中小企業でも実践可能な施策で大きな成果を出せる好例です。
4. 導入と改善のポイント
離職予防施策を効果的に導入するには、以下の点を押さえることが重要です。
- 段階的な取り組み: 全ての施策を一度に導入するのではなく、自社の課題に合わせて優先順位をつけ、段階的に取り組むこと。
- 定量的な効果測定: 離職率やエンゲージメントスコアなどを定期的に測定し、PDCAサイクルを回して改善を続けること。
- 経営戦略としての位置づけ: 経営層が離職予防を「人材への投資」と捉え、コミットメントを示すことが、取り組みを成功させる鍵です。これは、近年注目される人的資本経営の考え方にも通じます。

5. まとめ
離職予防は、単なるコスト削減策ではありません。従業員の成長を促し、組織の持続的発展を可能にするための「未来への投資」です。
本記事で紹介したように、オンボーディングの強化、キャリア支援、ワークライフバランスの推進、そして心理的安全性の確保といった多面的な施策を組み合わせることで、従業員が安心して長く働き続けられる環境を整えることができます。
企業は離職予防を通じて人材流出を防ぐだけでなく、組織の活性化と競争力向上を実現できるのです。自社の現状を把握し、一歩ずつ着実な離職予防施策を導入することで、持続的な成長を目指しましょう。
定着率改善の第一歩は「現状の見える化」から
本記事では、離職予防のための具体的な施策を数多くご紹介しましたが、これらの施策を闇雲に導入しても、必ずしも効果があるとは限りません。重要なのは、自社の離職の根本原因がどこにあるのかを正しく把握することです。
「社員がなぜ辞めてしまうのか?」 「どんな不満を抱えているのか?」
といった、社員一人ひとりの声やデータを正確に捉えることが、効果的な施策立案の第一歩となります。
株式会社MASTが提供する「Teichaku Marker(定着マーカー)」は、まさにその課題を解決するためのツールです。
Teichaku Markerは、従業員の行動特性と組織の離職理由を分析することで、離職リスクを可視化し、組織の課題を明確にします。これにより、勘や経験に頼るのではなく、データに基づいた効果的な離職予防策を講じることが可能になります。
Teichaku Marker(定着マーカー)でできること
- 離職リスクの可視化: 従業員満足度やエンゲージメントの状態をデータで把握し、離職予兆を早期に検知します。
- 退職理由の深掘り: 従業員が組織をどのように見ているかという本音を独自の分析ロジックで体系的に解明し、組織の根本課題を特定します。
- 施策効果の測定: 導入した施策の効果を定期的に測定し、PDCAサイクルを回すための客観的なデータを提供します。
Teichaku Markerの導入によって、無駄な施策にコストをかけることなく、最小限の投資で最大限の効果を得ることができます。
「最近、退職者が増えてきた…」 「離職の原因がわからず、対策が立てられない…」
そのようなお悩みをお持ちの企業様は、ぜひ一度、Teichaku Markerの無料相談にお申し込みください。 貴社の状況に合わせた最適な離職予防の道筋を、専任のコンサルタントがご提案します。
▶▶▶ Teichaku Markerの無料相談はこちらから ◀◀◀