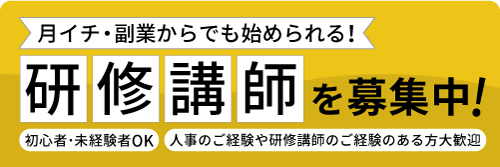データで証明する心理的安全性への投資効果:離職率14.2%超の壁を破る戦略的マネジメント

近年、企業の持続的成長の鍵として「心理的安全性」という概念が注目されています。しかし、単なる精神論として捉えるのではなく、経営リスクと投資対効果(ROI)の観点から戦略的に評価することが、現代の経営者、管理職には求められています。
本レポートでは、厚生労働省が公表する最新のデータに基づき、職場環境の整備が、いかにして日本の職場に潜む巨額の経済損失を回避し、高止まりする離職率という構造的な課題を解決し、さらに法的コンプライアンスを徹底する防波堤となるのかを、具体的な数字をもって証明します。特に、令和6年雇用動向調査で示された離職率14.2%という「人材流出の壁」を打破し、企業競争力を高めるための、データドリブンな戦略的マネジメント手法を詳述します。
1. 戦略的人事の課題:なぜ優秀な人材が定着しないのか
1-1. 離職率の現状把握:令和6年雇用動向調査に見る14.2%という数字の重み
企業の持続的な成長において、人材の定着は避けて通れない最重要課題です。厚生労働省が公表した令和6年「雇用動向調査」によると、全国の主要産業における離職率は14.2%という高い水準にあります。この数字は、企業がせっかく投資して育成した貴重な人的資本が、年間1割以上の割合で流出し続けている現実を示しており、採用・教育コストの増大、業務の非効率化、そして組織知の散逸を招いています。
この離職率を詳細に見ると、就業形態によって傾向が異なります。一般労働者の離職率が11.5%であるのに対し、パートタイム労働者の離職率は21.4%と、著しく高い数値を示しています。
さらに産業別に焦点を当てると、特に「宿泊業、飲食サービス業」では、一般労働者で18.1%、パートタイム労働者では29.9%という驚異的な離職率が確認されています。この高い流動性の背景には、単なる労働条件だけでなく、職場で感じられる「精神的な安全」の欠如が深く関わっていると分析されます。この14.2%、そして特定の産業で3割近くに達する離職率こそが、職場の心理的安全性の整備が急務であることを示す、最初の警告信号です。
1-2. 心理的安全性と人材定着の因果関係
離職率の高さがもたらすコストは、単に次の人材を採用する費用に留まりません。従業員が職場に留まるかどうか、すなわち人材定着の成否は、その職場で自身の意見、懸念、あるいはミスを率直に表明できるかどうか、という「心理的安全性」に強く依存します。
職場において心理的安全性が確立されている場合、従業員は失敗を隠す必要がなく、問題が顕在化する前に解決策を議論できます。これにより、個人の孤立やストレスの蓄積を防ぎ、結果としてエンゲージメントが向上します。逆に、意見を述べれば非難される、上司に相談すれば不利益を被る、といった職場では、従業員は問題や不調を隠蔽します。これが進行すると、従業員は燃え尽き、最終的に離職という形で企業から流出してしまいます。特に、高ストレス環境下にある従業員が声を上げられないことは、組織にとって大きな機会損失であり、離職率の改善には、この「声を上げる権利」を保証する組織文化、すなわち心理的安全性の確立が不可欠なのです。
2. 離職コストを上回る7.6兆円の隠れた損失の掘り起こし
2-1. アブセンティズムからプレゼンティズムへ:不調の可視化
心理的安全性が欠如していることによる経済的影響は、離職(アブセンティズム)という目に見えるコストに留まりません。さらに深刻なのは、メンタルヘルス不調を抱えながらも出勤し、生産性が著しく低下している状態、すなわち「プレゼンティズム」によって発生する隠れた損失です。
横浜市立大学COI-NEXT拠点Minds1020Labの研究成果など、厚生労働省関連データに基づく試算によると、日本の働く人のメンタルヘルス不調による経済的な損失は、年間7.6兆円という巨額に上ることが明らかになっています。この損失額は、日本のGDPの1.1%に相当し、精神疾患の医療費の約7倍以上という規模です。
この7.6兆円という数字は、単なる医療費の増大ではなく、「気分が沈む」「眠れない」といった不調を抱えた労働者が、出勤しながらも能力を十分に発揮できず、結果として社会全体の生産性に甚大な損失をもたらしている実態を、全国レベルで金額換算したものです。
心理的安全性が低い環境では、従業員は、不調を訴えれば「弱者」と見なされ、評価や昇進に悪影響が出ることを恐れます。そのため、病欠や休職(アブセンティズム)を選ぶ前に、不調を隠蔽しながら働き続ける(プレゼンティズム)ことを選択します。この隠蔽が、結果として年間7.6兆円という巨額の経済的打撃を企業にもたらしているのです。この隠れたコストを可視化し、心理的安全性の確保を予防的な投資と位置づけることが、経営層に求められています。
出典元:横浜市立大学プレスリリース
2-2. 高流動性産業における心理的安全性欠如の連鎖
前述したように、宿泊業、飲食サービス業といった産業では、パートタイム労働者の離職率が29.9%に迫るなど、極めて高い流動性を示しています。この高流動性の背後には、労働環境の特性と心理的安全性の脆弱性が連鎖する構造が存在します。
労働安全衛生調査のデータからは、仕事上のストレス要因として、近年「顧客、取引先等からのクレーム」の割合が最も上昇していることが指摘されています。
この二つの事実、すなわち「高流動性」と「顧客クレームの増加」を重ね合わせると、以下のような構造が浮かび上がります。顧客や取引先からの強い外部ストレスに直面した従業員が、そのストレスや不満、あるいは業務上の困難を、職場で安心して相談し、適切なサポートや防御を得られる環境(心理的安全性)がなければ、彼らは外部からのプレッシャーを一人で抱え込みます。その結果、心身の不調(プレゼンティズム)を経て、最終的に「離職」という形で職場から逃れることを選択してしまうのです。
したがって、特定の高リスク産業においては、職場における心理的安全性の確保こそが、外部ストレスに対する「組織的な防護壁」として機能し、離職コストと採用コストの劇的な削減を可能にする、最も費用対効果の高い戦略なのです。
3. 法的遵守の徹底:安全性が組織を守る防波堤となる
3-1. ハラスメント防止措置の戦略的意義
心理的安全性の確立は、単なる組織風土の改善に留まらず、企業の法的コンプライアンス、特にハラスメント防止措置の実効性を担保する上で極めて重要な意味を持ちます。
厚生労働省の指針に基づき、パワーハラスメント(パワハラ)を防止するための措置は、中小事業主を含む全ての事業主に令和4年4月1日から義務化されました。事業主は、セクシュアルハラスメント等の防止措置の経験を活かしつつ、パワハラ防止対策についても必要な措置を講じることが求められています。
この法的義務の中核となるのが、「相談(苦情を含む)に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備」です。具体的には、相談窓口をあらかじめ定め、従業員に周知し、担当者が内容や状況に応じて適切に対応できる体制が必要です。
ここで、心理的安全性の概念が、この法的義務を単なる「形式」から「実効性」へと変える鍵となります。従業員が、相談したことで不利益な取扱いを受けるのではないか、あるいは相談内容が外部に漏れるのではないかと懸念する場合、相談窓口は機能不全に陥ります。パワハラが発生している場合だけでなく、発生のおそれがある場合やハラスメントに該当するかどうか分からない場合であっても、働く人が「安全に」広く相談できる風土を醸成することこそが、法令遵守における最大の戦略的防御となります。
さらに、事業主は、妊娠・出産等に関するハラスメントや、育児・介護休業等に関するハラスメントについても防止措置を講じる義務があります。例えば、労働者が制度の利用を請求したい旨を上司に相談したところ、上司が請求を取り下げるよう言う行為は、制度利用の阻害行為として明確なハラスメントに該当します。管理職がこのような具体的な法的リスクを回避し、従業員が権利を行使できる安全な環境を整備することが、組織を法的リスクから守る防波堤となるのです。
出典元:厚生労働省「職場におけるハラスメント対策パンフレット」
政府広報オンライン「NOパワハラ なくそう、職場のパワーハラスメント」
3-2. ストレスチェックと職場環境改善の連動

メンタルヘルス対策の重要な法的措置として、ストレスチェック制度の実施は、全事業場で義務化されています。この制度を単なる義務の履行で終わらせず、心理的安全性の向上に活かすことが、戦略的マネジメントには不可欠です。
ストレスチェックの結果は、組織全体の高ストレス者や、特定の部門におけるストレスレベルの傾向を把握するための貴重なデータを提供します。このデータを、匿名性・公平性を担保しつつ、職場環境改善計画に連携させることが求められます。
心理的安全性の観点から見ると、ストレスチェックの「実施」そのものよりも、その結果を受けて組織が「行動」を起こすプロセスが重要です。従業員に対して、チェック結果が組織全体の改善、すなわち自分たちの職場環境の向上に役立てられているという透明性を示すことは、組織への信頼感を高め、結果として従業員のエンゲージメントを強化します。このデータに基づいたPDCAサイクルを回すことこそが、法令を遵守しつつ、健康経営の実現に向けた厚生労働省の指導に沿った戦略的なアプローチとなります。
出典元:厚生労働省「労働安全衛生法作業環境測定法の一部を改正する法律について(報告)」
4. 心理的安全性向上のための戦略的マネジメント実践論
4-1. 管理職の役割転換:コーチングと傾聴の導入
心理的安全性の成否は、現場を統括する管理職の日常的な行動に決定的に依存します。管理職は、これまでの「一方的に指示する人」という役割から、「対話を通じて問題解決をサポートする人」へと役割を転換する必要があります。この転換を支えるのが、厚生労働省関連機関が推奨する、組織コミュニケーションを円滑にするための基本姿勢である傾聴の技術です。
傾聴の実践は、以下の三つの具体的な行動から成り立ちます。
- 話を遮らずに最後まで耳を傾ける: 相手の話を最後まで聞くという行為は、信頼関係を築くための最初のステップです。管理職が性急に結論を求めたり、途中で自分の意見を挿入したりすることは、部下の意見の安全性を瞬時に損ないます。
- 適切なタイミングでの反応(相槌、うなずき): 相手に対して興味を持ち、自分自身もオープンな姿勢でいることを示すため、話を聞く際は適切なタイミングでうなずきや相槌を打つことを意識します。
- 深い理解を促す確認と質問: 相手の言葉を言い換えて「つまり、〜ということですね?」と確認したり、具体的な状況を掘り下げるための質問をしたりすることで、管理職は部下の意見や感情を正しく理解し、認識のズレを防ぐことができます。この確認作業を通じて、部下は「自分の意見が正確に受け止められた」と感じ、心理的安全性における信頼の土台が築かれます。
特に、テレワークの導入が進む現代においては、対面でのコミュニケーション機会が減少しています。管理職は、意識的にこれらの傾聴スキルを駆使し、非対面環境下でも信頼関係を維持・強化するための新たなコミュニケーションノウハウを確立することが期待されています。
4-2. 特定ストレス要因への具体的な対応策
前述の通り、労働安全衛生調査に見る「顧客、取引先等からのクレーム」の割合の上昇は、現場の従業員が受ける外部ストレスが増大していることを示唆しています。管理職は、この特定のストレス要因に対し、心理的安全性を担保するための具体的な防御策を講じる必要があります。
まず、ハラスメント防止の観点から、業務分担や安全配慮等の観点から、客観的にみて業務上の必要性に基づく言動と、ハラスメントに該当する言動との線引きを明確化することが重要です。これにより、従業員は、自身が業務を遂行する上で「どこまでが安全な領域なのか」を理解できます。
管理職は、チームメンバーが顧客や取引先からの不当な要求やクレームに直面した際、彼らの感情や意見を傾聴によって受け止める「心理的なバッファ」としての役割を果たさなければなりません。また、クレーム対応後の適切なフォローアップ、業務分担の見直し、そして「それはハラスメントではないか?」という議論を安全にできる体制を現場で構築することが、外部ストレスの組織内での吸収と解消につながり、心理的安全性を維持する具体的な対策となります。
出典元:厚生労働省「令和5年労働衛生安全調査(実態調査)の概況」
厚生労働省「職場におけるハラスメント対策パンフレット」
4-3. 定着率改善に向けたPDCAサイクル

心理的安全性の向上は一度きりの施策ではなく、継続的なプロセスです。企業は、施策の効果を測定し、改善につなげるPDCAサイクルを回す必要があります。
その第一歩として、組織の課題は規模や形態によって異なるという認識のもと、定期的なアンケートによる状況把握が欠かせません。ストレスチェックの結果や離職率の推移だけでなく、匿名性の高いアンケートを通じて、職場のコミュニケーション課題や、従業員が感じる心理的安全性のレベルを定量的に把握します。
次に、課題が特定された部門に対し、管理職による傾聴スキルの研修導入や、ハラスメント防止のための再発防止策を講じるなどのアクション(Do)を実行します。
その後、一定期間を経て、離職率や従業員の満足度、ストレスレベルの変化を再測定し、効果を検証(Check)します。例えば、高ストレス産業の離職率(例:29.9%)が改善したかを検証します。
そして、この検証結果に基づき、部門間の連携強化や、テレワーク下での新しいコミュニケーションノウハウの確立など、次なる改善(Action)へとつなげます。この継続的な改善サイクルこそが、高止まりする離職率14.2%の壁を確実に破り、人的資本を最大化するための戦略的マネジメントの本質となります。
出典元:政府広報オンライン「NOパワハラ なくそう、職場のパワーハラスメント」
5. まとめ:心理的安全性という人的資本投資が未来の競争力を生む
本レポートがデータをもって示した通り、心理的安全性の確保は、現代の企業経営において、感情論や理想論ではなく、年間7.6兆円にも上る生産性損失の回避、そして離職率14.2%超という構造的な人材流出リスクを抑制するための、最も合理的な「戦略的投資」です。
経営層、管理職の皆様は、厚生労働省の指針が示すハラスメント防止措置の義務化と、コミュニケーション円滑化の指導を、単なるコンプライアンスの枠組みとしてではなく、企業の競争優位性を確立するためのチャンスとして捉えるべきです。
管理職による傾聴スキルの徹底、ストレスデータの活用、そして継続的な職場環境改善のPDCAサイクルを通じて、心理的安全性という強固な土台を築き上げることこそが、組織の持続可能性と、未来の競争力を生み出す鍵となります。
データに基づき「離職の壁」を破る組織改善ツールのご案内
本レポートで示されたように、理論や法令の理解に加え、実際の心理的安全性をデータで可視化し、継続的なPDCAサイクルを回す実践が不可欠です。しかし、「どこから手を付ければいいか分からない」「自社の課題が特定できない」といった悩みを抱える経営者や管理職の方も多いでしょう。
そうした課題に直面する企業様のために、株式会社MASTが提供する組織改善ツール『Teichaku Marker(定着マーカー)』が、貴社の戦略的マネジメントを強力にサポートします。
Teichaku Markerは、本記事で指摘した「高止まりする離職率」を改善することに特化しており、導入事例では離職率20%から5%への大幅改善を実現した実績があります。
このツールは、単なる従業員満足度調査ではなく、従業員の声やデータから職場の心理的安全性のレベル、コミュニケーションの質、ストレス要因を特定します。特に、メンバーが発言しやすい環境(情報共有の促進)や、ミスの迅速な報告といった、心理的安全性の鍵となる要素を定量的に把握し、データに基づいた改善アクションを可能にします。
「7.6兆円の隠れた損失」を避け、人材定着と企業競争力を高めるための第一歩を踏み出しませんか?
貴社の現在の職場環境と離職リスクを専門家が分析する無料相談を受け付けております。データドリブンな組織改善にご興味のある方は、ぜひこの機会にお気軽にご相談ください。
▶▶▶ Teichaku Markerの無料相談はこちらから ◀◀◀