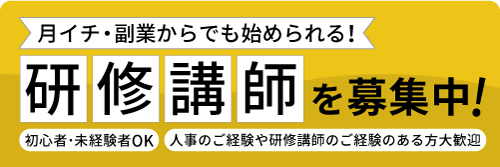コスト削減の鍵は【早期離職防止】:若手社員の定着率を5ステップで改善する実践ロードマップ

企業が持続的な成長を遂げ、競争力を維持する上で、最大の懸案事項の一つが【早期離職防止】です。多くの企業が「人手不足」に直面する中、特に若手社員の定着率向上は、単なる人材マネジメント上の課題ではなく、企業の財務健全性を直接的に脅かす「コスト問題」として、経営戦略の最優先事項として捉える必要があります。
厚生労働省の最新のデータ分析によると、2021年3月に卒業した大学卒就職者のうち、就職後3年以内の離職率は34.9%に達し、これは3年連続の上昇傾向を示しています。これは、企業が採用と育成に投じた初期投資の約3分の1が無に帰していることを意味します。定着率の改善は、失われ続けるコストを削減し、企業の競争力を高めるための最も効果的な財務戦略です。
本レポートは、【早期離職防止】を最重要課題と認識する経営者や人事担当者向けに、厚生労働省の統計データに基づいた離職コストの具体的な試算を公開します。これにより、なぜ定着率の改善が最も効果的な「コスト削減」戦略となるのかを明確にし、その上で、今すぐ実行できる「実践ロードマップ(5ステップ)」と、特に離職率が高い産業向けのカスタマイズ戦略を、具体的な実行計画とともに詳細に解説します。
1.若手離職がもたらす致命的な費用とリスク
若手社員が早期に離職することで発生する費用は、単に次の採用にかかる広告費だけではありません。採用活動の開始から離職後の事務手続きに至るまで、目に見えにくい「隠れた損失」が企業のキャッシュフローを圧迫します。このコストを削減することが、すなわち【早期離職防止】の目的となります。
大卒離職率34.9%から逆算する年間コスト損失シミュレーション

大学卒の3年以内離職率が34.9%という事実は、企業が若手社員を3人採用した場合、そのうち約1人は3年以内に離職することを意味します。この高い離職割合が、企業に継続的なコスト損失を生み出しています。
若手社員1名が離職する際に発生する総コストは、以下の三つの要素に分解されます。
- 新規採用コストの再投資(直接費用):
離職が発生すれば、当然ながらその穴を埋めるために次期採用活動への再投資が必要となります。厚生労働省関連のアンケート調査によると、正社員の採用1件あたりにかかる平均コストは、採用手法によって9,000円から914,000円の範囲で分布しており、この採用単価の損失は即座に発生します。離職率が高い企業ほど、この採用サイクルを繰り返すことになり、【早期離職防止】対策を講じない限り、採用費用は雪だるま式に増大します。 - 育成・教育投資の損失(直接費用):
入社後の育成にかかる初期投資も回収できなくなります。厚生労働省の能力開発基本調査に基づくと、企業が労働者1人あたりに支出するOFF-JT(OJT外の訓練)費用は平均1.5万円、自己啓発支援費用は平均0.4万円です。これはあくまで平均額であり、特に専門職や高度なスキルが求められる職種では、この初期投資額は遥かに高くなります。例えば、若手社員が3年間勤務した場合、育成投資総額は約5.7万円〜となりますが(1.9万円/年 x 3年)、離職が発生すればこの投資回収はゼロとなります。この積み重ねられた初期投資額が、離職によって無駄になり、次期採用者への再投資を強いられるため、実質的なコスト損失は倍増します。 - 離職後の管理・引き継ぎコスト(間接費用):
離職者の業務引き継ぎ、残されたメンバーの業務負荷増加、退職手続き、そして離職率悪化による採用活動効率の低下など、離職後もコストは発生し続けます。新卒者の離職後に発生する平均コストは53.1万円と試算されており、この事務処理や引き継ぎにかかるコストは無視できません。
※試算方法
内閣府によると、年収600万の人が6ヶ月間休職した場合、周囲の従業員に与えるコストとして約224万円と報告されています。計算を単純化すると、大卒の新卒年収は約285万円であり、3ヶ月間不在になったコストは新卒で53.1万円(224万円×285万円/600万円×3/6ヶ月)となります。
出典元:厚生労働省「採用における人材サービスの利用に関するアンケート調査」
これらのデータに基づき、若手社員1名の離職が企業にもたらす総損失は、機会損失を除いても最低で100万円以上に上ると概算されます。このコスト構造を詳細に分析すると、離職後の事務処理や引き継ぎに発生するコスト(53.1万円)は、企業が若手社員の育成に年間投資する平均額(OFF-JT 1.5万円+自己啓発 0.4万円=1.9万円)の約28倍にも及びます。
この分析は、予防的な定着支援への投資が、損失コストと比較して極めて費用対効果が高いことを示しています。定着率の改善は、この百万単位の損失を直接削減する、極めて重要なコスト削減戦略にほかなりません。
| 早期離職による若手社員1名あたりの想定コスト損失(厚生労働省関連データに基づく) | |
| <コスト要素> | <試算範囲とデータ根拠> |
| 新規採用コスト(再投資分) | 数十万円〜(採用手法により9千円~91.4万円) |
| 育成・研修費の損失(3年分) | 約5.7万円〜(OFF-JT 1.5万円/年、自己啓発 0.4万円/年) |
| 離職後の手続き・管理コスト | 53.1万円(新卒離職者の平均コスト) |
| 合計総損失 (機会損失除く) | 最低100万円以上 |
出典元:厚生労働省「採用における人材サービスの利用に関するアンケート調査」
2.定着率改善のための実践ロードマップ:5つのステップと実行計画
若手社員の定着率を向上させ、長期的なコスト削減を実現するためには、体系的なアプローチが必要です。ここでは、特に大学卒の離職者が1年目よりも2年目(12.3%)や3年目(10.3%)で多くなる傾向 を踏まえ、初期の組織適応だけでなく、その後の成長を支援するための5つの実践ステップを提案します。
出典元:厚生労働省「新規学卒就職者の離職状況(令和3年3月卒業者)」
ステップ1:離職予兆を把握する「定期的な不満・不安の把握メカニズム」
離職は突発的に起こるわけではなく、多くの場合、不満やキャリアへの不安が蓄積した結果です。特に大卒者の場合、入社直後の環境適応期を過ぎた2年目以降がハイリスク期間となります 。この期間に、不満が表出する前に予兆を把握するメカニズムの構築が不可欠です。
実行計画:
- 定期的なエンゲージメントサーベイと1on1の義務化: 定期的な(四半期ごとなど)エンゲージメントサーベイを実施し、同時に、上司との1on1面談を義務化します。この面談は、人事評価とは明確に切り離し、「心理的安全性の確認」と「精神的なケア」に特化した設計とすることが重要です。
- 非公式なディスカッションの場: 若手社員が上司には言いづらい不満や課題を早期に吸い上げるために、ワールドカフェ形式などの非公式なディスカッションの場を設けることが有効です。こうした互いに近い立場の若手同士の交流は、精神的なケアや課題共有を促し、【早期離職防止】の低減に役立つことが、地域の中小企業における定着支援事業でも確認されています。
ステップ2:公平性を担保する人事評価制度の策定と公開
若手社員が離職を選択する大きな要因の一つに、自身の努力や成果が正当に評価されていないと感じる「不公平感」があります。成長意欲の高い若手層に対し、企業が真摯に応えるためには、制度の透明性と客観性が必須です。
実行計画:
- 評価基準の明確化と公開: 目標設定(MBO)と評価基準(コンピテンシー)を全社員に公開し、評価の客観性を確保します。
- 評価プロセスの開示と教育: 誰が、どのようなプロセスで評価を行うのかを明確にし、評価者による恣意性を排除します。また、評価者(マネジメント層)に対する適切な評価スキルの教育を徹底します。
- フィードバックの義務化: 評価結果を一方的に伝えるのではなく、評価結果に基づき、今後の成長に必要な行動やスキルを具体的に指導するフィードバック面談を評価サイクルに必ず組み込みます。
公正で透明性の高い人事・教育訓練制度の充実は、厚生労働省がキャリア形成支援として推奨する「グッドキャリア企業」の基盤となる取り組みです。
ステップ3:若手の成長意欲に応えるキャリアデザインのサポート体制構築
大卒者の離職が2年目以降に集中することは、初期の期待値ギャップよりも、「この会社で将来的に成長できるのか」というキャリアへの不安が主要な離職動機となっている可能性が高いことを示唆しています。彼らの成長意欲に応える仕組みが、【早期離職防止】の決め手となります。
実行計画:
- キャリア面談の導入とキャリアビジョンの可視化: 年に一度、人事部門または専門のキャリアコンサルタントによる「キャリアビジョン面談」を実施し、社員自らが5年後、10年後の将来像を考える機会を提供します 。これにより、会社が個人の成長を真剣に考えているというメッセージを伝えます。
- 育成投資の見える化: 企業が労働者一人あたりに投資している教育訓練費(OFF-JT 1.5万円、自己啓発 0.4万円)を、単なる経費ではなく「社員の未来への投資」として具体的に伝え、企業の育成に対する強いコミットメントを示します。
- 社内公募・ローテーション制度の積極活用: 成長機会の停滞を防ぐため、挑戦意欲の高い若手が、現部署に留まらず新しい職務や部署を経験できる社内異動・公募の仕組みを制度化し、キャリアの選択肢を提供します。
ステップ4:マネジメント層の育成力強化とOJTの質向上

若手育成の中核であるOJT(オン・ザ・ジョブ・トレーニング)の質が、定着率を左右します。厚生労働省のデータによると、計画的なOJTを正社員に対して実施した事業所は61.1%にとどまっており、約4割の企業で育成が場当たり的になっている可能性があります。このOJT実施率の低さ(61.1%)は、約4割の企業で若手育成の質が属人化・形骸化していることを示唆しており、若手のスキルアップが停滞し、結果として2年目以降の離職につながる大きな要因です。
定着率改善をコスト削減戦略として実行するには、まずOJT実施率を100%に近づけることが必要です。
実行計画:
- OJT実施計画の可視化と義務化: 全ての部署において、年間を通じて若手社員の習得すべきスキルと評価基準を明文化したOJT計画書を作成し、実施を義務化します。
- 指導者育成プログラム(TTT)の導入: OJTトレーナーやマネジメント層に対し、【早期離職防止】に特化したコーチング研修(ティーチング、適切なフィードバック技術、傾聴力)を必須とします。これにより、OJTの「質」を高め、若手の成長と定着に直結する育成環境を整備します。
- 計画的OJTの実施: 計画的なOJTの実施率を100%に近づけることで、若手のスキルアップの停滞を防ぎ、2年目以降の離職リスクを大幅に低減させます。
ステップ5:働き方とウェルビーイングの基盤整備
キャリア支援や評価制度の改善は重要ですが、それらが機能する大前提として、社員が安心して健康的に働ける環境基盤の整備が不可欠です。
現在、厚生労働省の調査結果によると、教育訓練休暇制度を導入している企業は7.5%、教育訓練短時間勤務制度の導入企業は6.2%と、柔軟な働き方を支援する制度の普及率は依然として低い水準にあります 。
実行計画:
- 柔軟な制度の導入検討: 教育訓練休暇制度(導入企業7.5%)、教育訓練短時間勤務制度(導入企業6.2%)の普及率が低い現状を打破するため、これらの制度導入を積極的に検討します。これにより、若手が仕事と自己啓発や私生活を両立できる環境を提供し、長期的な定着を支援します。
- 長時間労働の是正と残業の削減:【早期離職防止】の観点から、残業時間の削減目標を設定し、マネジメント層が率先して定時退社を促す企業文化を醸成します。過度な労働負荷は、若手社員のエンゲージメントと健康を損なう最大の要因です。
- ウェルビーイング施策の可視化: 従業員が心身ともに健康でいられるよう、ストレスチェックの実施や外部EAP(従業員支援プログラム)サービスを導入し、利用手続きを簡素化するなど、若手社員が気軽に相談できる体制を整え、利用しやすい環境を整備します。
3.厚労省データに基づく産業別ハイリスク層へのカスタマイズ戦略
若手離職の課題は産業特性によって大きく異なります。厚生労働省のデータに基づき、特に離職率が高い産業が優先すべき、カスタマイズされた定着戦略を提案します。
離職率65.1%の宿泊・飲食業界が優先すべき即効性のあるコミュニケーション施策
宿泊業、飲食サービス業は、高校卒の離職率が65.1%、大学卒でも56.6%と、全産業の中で最も高い離職率を記録しています 。この業界の特性(高頻度な入れ替わり、業務の即時性、長時間労働傾向)を踏まえると、即効性と低コストを実現できる施策が優先されます。
カスタマイズ戦略(即効性重視):
- マイクロフィードバックの徹底: 業務サイクルが速い特性を活かし、日次またはシフト終了時など、短いスパンで感謝や具体的な改善点を伝えるフィードバックを徹底します。これにより、コストをかけずに若手の承認欲求を満たし、モチベーションの維持を図ります。
- 業務マニュアルの標準化: 離職率の高い1年目社員の不安を軽減するため、業務を徹底的に標準化し、習熟度を可視化するステップアップテストを導入します。これは、計画的なOJTが難しい現場環境を補完し、早期の戦力化と自信の獲得を支援します。
- ピアサポート制度の導入: メンター制度よりもカジュアルな「バディ制度」や「サポーター制度」を導入し、業務負担が大きい若手社員同士が、横のつながりを通じて精神的なサポートを行う仕組みを構築します。
出典元:厚生労働省「新規学卒就職者の離職状況(令和3年3月卒業者)」
教育・学習支援業界における若手育成と定着支援のポイント
教育、学習支援業は、大学卒の3年以内離職率が46.6%と宿泊・飲食業に次いで高い水準にあります。この業界は、高い専門性と同時に、業務量が多く精神的な負担が大きいという特性を持ちます。若手は「教育」という職務の意義は理解しつつも、過重労働や成長の限界に直面しやすい傾向があります。
カスタマイズ戦略(成長と連携重視):
- 外部連携を通じたモチベーション維持(ワールドカフェ形式の活用): 若手社員に対し、地域の中小企業で効果が確認されているワールドカフェ形式 を応用し、学生や外部の関係者とのディスカッションの場を定期的に設けます。若手社員(入社1~3年目)と学生(大学3年生中心)が互いに近い立場でディスカッションを行うことで、若手社員は自身の業務が学生に与える影響を再認識し、業務の意義や自社の魅力を外部からの視点で確認する機会を得られます。これは、特に成長志向の高い若手のモチベーション維持に有効であり、インターンシップの成果報告の場としても活用可能です。
- 専門スキル研修への戦略的投資の明確化: 専門職である特性を考慮し、労働者一人当たりのOFF-JT費用平均(1.5万円)よりも高い水準で、専門性の向上に直結する外部研修への予算を確保します。教育業界において、この投資はコストではなく、サービスの質を維持・向上させるための戦略的投資と位置づけるべきです。
- メンタルヘルス支援の可視化: 精神的な負担が大きい業界であるため、外部EAP(従業員支援プログラム)サービスを導入し、利用手続きを簡素化するなど、若手社員が気軽に相談できる体制を整え、利用しやすい環境を整備します。
出典元:厚生労働省「新規学卒就職者の離職状況(令和3年3月卒業者)」
4.まとめ【早期離職防止】は未来へのコスト削減投資である
本レポートで提示したように、若手社員の【早期離職防止】は、企業の持続的成長のための最重要経営戦略です。データ分析が示す通り、離職による年間最低100万円超のコスト損失は、予防的な定着支援投資を遥かに上回ります。定着率の改善は、感情論や理想論ではなく、企業の財務健全性を守るための最も効果的な「コスト削減」戦略として実行されるべきです。
実践的な5つのステップ(離職予兆把握、評価の公平性、キャリア支援、OJT強化、環境整備)は、若手社員が直面する成長の停滞やキャリアへの不安といった課題を体系的に解決するためのロードマップとなります。特に、離職率の高い宿泊・飲食業、教育・学習支援業といった高リスク産業の企業は、厚生労働省のデータ と自社の現状を照らし合わせ、産業特性に合わせたカスタマイズ戦略を即座に実行することが、【早期離職防止】という未来へのコスト削減投資に繋がります。
【早期離職防止】実現のために:若手定着の仕組みを構築する
本記事では、厚生労働省のデータに基づき、若手社員の【早期離職防止】がいかに重要なコスト削減戦略であるかを解説し、具体的な5つの実行ステップを提示しました。しかし、「不満・不安の把握メカニズム」の構築や、「産業特性に合わせたカスタマイズ戦略」の実践は、人事担当者の経験やリソースだけでは限界があり、継続的な効果測定や改善が難しいという課題があります。
100社以上の実績から生まれた「Teichaku Marker(定着マーカー)」のご案内
若手社員の定着を確実にコスト削減に繋げたいとお考えの企業様へ。株式会社MASTが提供する「Teichaku Marker(定着マーカー)」は、本記事で解説した「離職予兆の把握」と「施策のカスタマイズ」を科学的に実現するためのソリューションです。
Teichaku Markerで実現できること:
- 定着の仕組み化と離職要因の特定: 100社以上の実践データから生まれた独自の分析技術に基づき、貴社の若手社員やリーダーの離職防止に効果的な具体的な施策を明確にします。
- コスト削減に直結する課題解決: 属人的な対策に頼らず、若手社員の定着度を診断し、コスト損失を最小限に抑えるための離職要因分析を専門的に行います。
- 行政・自治体向けの知見を活用: 介護/福祉事業や行政・自治体向けの人材育成・メンタルヘルスサポートで培ったノウハウを応用し、より専門的かつ実践的な定着支援をご提供します。
無料相談受付中:貴社の【早期離職防止】戦略を専門家にご相談ください
「自社の若手離職率が高い産業に該当しているが、具体的な施策が打てていない」「現在の評価制度やOJTが機能しているか不安がある」といったお悩みをお持ちの場合は、ぜひ一度、Teichaku Markerの専門家にご相談ください。
貴社の現状をヒアリングし、最も費用対効果の高い【早期離職防止】のためのロードマップをご提案いたします。
まずは、離職要因分析・定着度診断に関する無料相談をお気軽にお申し込みください。▶▶▶ Teichaku Markerの無料相談はこちらから ◀◀◀